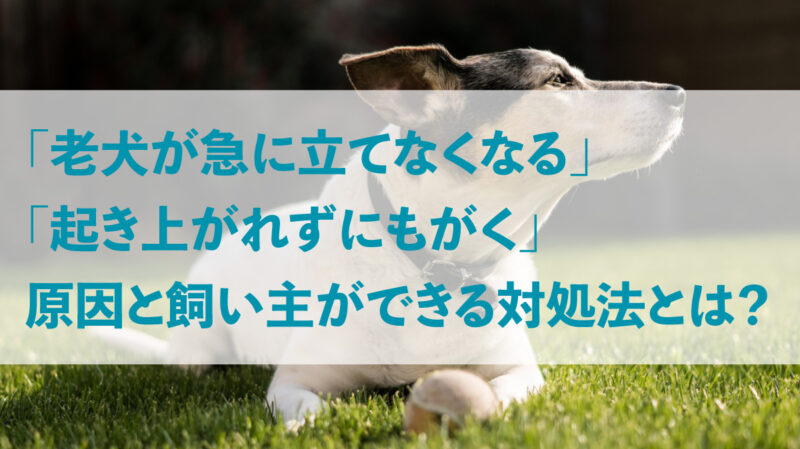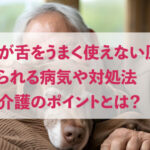自力で起きれなくなくなった老犬がいます。
起こしても何度も転んでしまいます。
何か良い方法はないでしょうか?
飼っている犬が老犬となり、自力で立ち上がれず、苦しそうにしている姿を見ると不安になりますよね。
「ただの老化なのかな…」
「何か病気じゃなければいいけど…」
「この子にできることはないのか…」
愛犬が起き上がれずにいる原因を知り、早く解決したいものです。
そこで本記事では、同じ症状の犬や飼い主からの情報に獣医師や専門家の意見を加え、老犬が起き上がれない原因と、自宅でできる介助や対処法を解説します。

2016年、日本大学生物資源科学部獣医学科卒。同年4月から、東京都内のペットショップ併設の動物病院に勤務。犬・猫・ウサギ・ハムスターの診療業務を行う傍ら、ペットショップの生体管理や、動物病院の求人管理や、自社製の犬猫用おやつやフードの開発に携わる。
2023年より1年間、分院長を経験し、2024年にフリーランス獣医師として独立。現在は診療業務の他、電話での獣医療相談や、ペット用品の商品監修、記事作成など幅広い業務を行っている。
老犬が立てない。起き上がれずにもがく原因とは?
老犬が自力で起き上がれず、もがいてしまうのには特定の原因があります。
ひとつは、加齢に伴う身体機能の衰え。
そしてもうひとつは、特定の病気や障害が影響しています。
それぞれ以下で詳しく解説します。
身体機能の衰え
人と同じく、犬も歳をとると筋肉が徐々に無くなり、全身の筋力が低下します。
特に支える力を必要とする「後ろ足」の筋力の低下が顕著に現れ、踏ん張って立ち上がることが難しくなるのです。
実際、シニア犬には、
- 立ち座りに時間が掛かる
- 歩くスピードが遅くなる
- 後ろ足を引きずって歩く
などの変化がよく見られます。
筋力が落ちてくると、起き上がろうとしてもうまく力が入らず、足が滑ってしまったり、バランスを崩してしまったりして、もがくような仕草を見せることがあります。
このような「加齢による筋力の衰え」は、概ねゆっくり進行するので、急を要する危険性は低いとされています。
しかし、そのまま放っておくとさらに筋力が低下し、いずれ寝たきりに近い状態になる恐れもあります。
散歩の距離が徐々に短くなったり、ちょっとした段差でつまずいていたら、それは筋力が落ちているサインかもしれません。
無理のない範囲で、適度に散歩やリハビリ運動を続けて、筋力を維持することが重要になります。
関節の痛み・疾患
老犬が起き上がれない原因で最も多いのが「関節の問題」です。
犬は歳を取ると関節炎や関節症になりやすく、一度発症してしまうと治すことができません。
関節症の中には、後ろ足や腰の関節(股関節や膝関節)の関節軟骨がすり減り、痛みや関節の腫れ、関節が変形していく「変形性関節症」があります。
関節疾患に多い「前十字靭帯断裂(前十字靱帯が切れてしまう)」によって足を引きずるようになり、変形性関節症を引き起こしてしまうのです。
これは大型犬に多く、体重が重い分、痛みも強くなってしまいます。
一方で、軽量な小型犬でも「膝蓋骨脱臼(パテラ)」という、膝蓋骨が正常な位置からズレる症状が起きると、その痛みで立てなくなることがあります。
では実際に、関節の問題を抱える犬はどれほどいるのでしょうか。

こちらは獣医師を対象とした「犬の骨活」に関する調査です。
「普段の診察の中で、加齢に伴い関節の不調を訴えるケースはどの程度あるか?」
という質問に対し、約9割もの方が「多い」と回答しています。

また、早いうちから骨活のケアを行うことにより、9割以上の獣医師が「犬の健康寿命が延びると思う」と答えています。
もしも、愛犬が次のような行動をとっていたら、関節の痛みを感じている可能性がありますので、獣医師に診てもらいましょう。
- しばらく元気がない
- 走ったり散歩したがらない
- 足を引きずっている
- 立ち上がるのが遅い、辛そう
- 段差を嫌がる
そして関節の不調を改善するためには、関節サポートのフードといった栄養面のケアと、適度な運動を含めた総合的な骨活が必要です。
神経系の疾患(脊髄・脳の問題など)
高齢犬で神経系の病気が原因で立てなくなるケースもあります。
代表的なのは脊椎・脊髄の障害です。
例えば、椎間板ヘルニアは、椎間板が変性して飛び出し脊髄を圧迫することで起こる病気で、以下の関節炎と同じような症状が見られます。
- 後ろ足がふらつく
- 後ろ足が立たない
- 段差をいやがるようになる
- 抱き上げた時に痛がる
症状が悪化すると、不全麻痺が進行し「歩行できない」「痛みを感じない」ようになります。
また、「変性性脊髄症(DM)」という神経の難病も高齢犬で発症することがあります。
これは、ウェルシュ・コーギーやジャーマンシェパードなどで報告されており、10歳前後から発症することが多い病気です。
DMは痛みが無いものの、後肢の麻痺が徐々に進行し、最終的には立てなくなってしまいます。
残念ながら、現在では有効な治療法は確立されていないため、進行を遅らせるケアや車椅子の利用などの介護が中心となります。
参考:岐阜大学動物病院「ウェルシュ・コーギーの変性性脊髄症 Degenerative Myelopathy(DM)in Welsh Corgi」
この他、脳卒中(脳梗塞)や脊髄梗塞のような、ある日急に倒れて起き上がれなくなる神経障害もあります。
愛犬の歩き方がおかしい、立ち上がれない、つまずいてもがくといった様子が見られたら、神経系の疾患の可能性もあると考えておきましょう。
前庭疾患など平衡感覚の異常
老犬に多く見られる前庭疾患(いわゆる「老犬のめまい」)も、起き上がれない原因のひとつです。
前庭とは内耳にある平衡感覚をつかさどる器官で、ここに異常が起こると激しい「めまい」や「ふらつき」が発生します。
ほとんど前触れもなく発症し、起き上がろうとしてもバランスが取れず何度も転んでしまうため、犬自身もびっくりしてしまいます。
前庭疾患には以下の症状が挙げられます。
- 頭が傾いて固定される
- 眼球が細かく揺れる(眼振)
- まっすぐ歩けず同じ方向に旋回する
- 嘔吐や過度なよだれ
これらの症状が出た場合、できるだけ早く動物病院へ連れて行ってあげてください。
幸い前庭疾患の多くは、適切な治療と時間経過で回復に向かいますが、発症直後の数日〜1週間程度は歩行補助や食事・排泄の介助が必要になります。
その他の考えられる原因
上記以外にも、外傷や急性の病気によって老犬が立てなくなることがあります。
高齢犬は骨も弱くなっているため、ちょっとした段差から転ぶだけで骨折することがあります。
さらに、重度の心臓病による失神や低血糖発作など、足腰と関係ない要因で倒れてしまう場合もあります。
こうしたケースでは、突然、愛犬が起き上がれなくなるため、きっと飼い主さんも驚き慌てることでしょう。
いざその時慌てないよう、普段から愛犬の様子をよく観察し、必要に応じて獣医師の診断を仰ぐことが大事です。
続いて、犬が起き上がれない時の具体的なサインを解説します。
起き上がれない老犬に見られるサインと注意点
愛犬が起き上がれずもがいていたら、飼い主さんは何を手掛かりに原因に気付けばよいのでしょうか。
以下は主なサインや症状です。
立ち上がりに時間がかかる・嫌がる
伏せや寝た姿勢からすぐに立ち上がれず、何度も足を踏み直したり、前足で床を掻くようにもがく姿が見られます。
立ち上がるのに時間がかかる、または立つこと自体を嫌がるようになるのは、老犬にとって「動くことそのものが負担」になっているサインです。
関節や筋肉に痛みを感じている場合、無理に立ち上がろうとせず、横になったまま飼い主の様子を伺うような視線も送ります。
後肢のふらつき・つまずき
立ち上がった後も後ろ足に力が入らず、ふらついたりヨロヨロと歩くことがあります。
「段差や階段で踏み外す」
「滑りやすい床で脚が開いてしまう」
「足を取られて転んでしまう」
といった場面に遭ったら注意が必要です。
こうした状態を放置すると、関節を痛めてさらに動けなくなる悪循環に陥る可能性があります。
散歩や運動を嫌がる
大好きな散歩に行きたがらなくなったり、少し歩くと座り込んでしまう場合、関節痛や身体の不調、筋力の衰えなど様々な原因が考えられます。
例えば、散歩の途中で歩きたがらなくなったり、途中で抱っこをせがむような場合、体に何かしら負担がかかっているかもしれません。
姿勢や歩き方の変化
「常に頭を低く下げて歩く」「腰が落ちてお尻がふらつく」「尾を下げたまま振らなくなる」といった姿勢の変化も見逃せません。
左右どちらかに体が傾いている場合は、前庭疾患や脳の問題の可能性があります。
また、後ろ足を引きずる(ナックリング)動作が見られるときは神経症状の疑いもあります。
排泄の失敗やベッドでの粗相
自力で立てない状態が続くと、トイレの場所まで間に合わずおもらししてしまうことがあります。
急にうまくトイレができなくなったら、立ち上がるのが困難だったり認知機能の低下が考えられます。
排泄の失敗は犬自身もショックを受けるので、叱らず受け止めてあげてください。
鳴き声や表情の変化
「クーン」と助けを求めるように鳴いたり、痛みから吠えたり唸ることもあります。
また、普段おとなしい犬が、飼い主に対して唸ったり噛もうとしたら、強い痛みや極度のストレスのサインです。
老犬は不調を言葉で訴えられないので、鳴き声や表情から気持ちを汲み取ってあげましょう。
以上のようなサインが見られたら、まずはその症状が急に現れたものか、それとも徐々に出てきているのかを見極めましょう。
そして、
1.「いつから」
2.「どのような症状」
3.「何回」
といった情報があると、獣医師も的確に判断しやすくなります。
続いては、犬が起き上がれなくなった時に注意すべき点を解説します。
老犬が立てずにもがいている時に注意すべき点
老犬が起き上がれずもがいているとき、飼い主さんはどのようにサポートすれば良いでしょうか。
以下で注意すべきポイントを挙げます。
安全の確保と転倒防止
愛犬がもがいているときは、周囲にケガの原因となる家具や硬い物がないか確認しましょう。
必要に応じて体に毛布やタオルを掛け、暴れても体を保護できるようにします。
また、一時的にケージやサークルに入れるもの良いです。
無理をして歩こうとすると、転んで二次的な負傷を招きかねないので、落ち着くまでは安静にさせましょう。
抱っこの仕方、歩行補助具の利用
起き上がれない愛犬を抱き上げる際は、できるだけ体に負担をかけないようにします。
大型犬の場合、飼い主一人で抱えるのは難しいので、介護用ハーネスなどを利用すると良いです。
後ろ足用のハーネスや、胴着型の歩行補助具を使うことで、飼い主さんの負担も軽くなります。
小型犬も体を痛めないように、胸と腰をしっかり支えて持ち上げてください。
ベッド周りの整理
自力で起き上がれない時間が長くなると、同じ姿勢で寝続けることで床ずれが起きやすくなります。
床ずれを防止するには、2~3時間おきに体位を変えてあげることです。
また厚めのマットを敷いたり、大きめのクッションを置くなどして、愛犬が落ち着ける体勢を探ってみてください。
そしてお尻や肘など、骨が当たる部分の皮膚が赤くなっていないか、排泄物で皮膚が荒れてないかなどもチェックしましょう。
歩けなくなるとトイレも行けなくなるので、介護用のオムツもつけてあげましょう。
水やご飯をサポートしてあげる
寝たきりに近い状態になると、水のある場所まで自分で行けなくなったり、ご飯をうまく食べれなくもなります。
そのため飼い主さんは、犬の口元まで運んで飲ませたり、流動食や強制給餌(きょうせいきゅうじ)をする必要があります。
病気以外には、老犬は舌の筋力低下や、口が開かないといった衰えもあります。
老犬へのご飯のあげ方については以下の記事で詳しく解説しています。
-

-
老犬が舌をうまく使えない原因。考えられる病気や対処法:食事介護のポイント
老犬がうまくご飯を食べられません。 何か良い方法はありますか? 老犬が食事を残したり、舌をうまく使えなくなっていませんか? 実はこれ、加齢や体調の変化が関係している可能性があります。 シニア期に入った ...
続きを見る
動物病院へ連れて行く
「愛犬が起き上がれない」
「急に立てなくなった」
「頑張って立とうと、ずっともがいている」
このような症状が見られたら、基本的には動物病院へ連れて行き獣医師に相談すべきです。
「どのタイミングで病院に連れて行くべきか…」
と判断に迷うかもしれませんが、症状が悪化すればその分できる処置も限られてしまいます。
特に、
- 強く鳴き続ける
- 前足まで麻痺や力の入らない様子がある
- 意識がもうろうとしている
といった症状が見られたら、緊急性が高く、放置すれば命に関わる状態につながりかねません。
普段からかかりつけの動物病院を持って、連絡を取り合い夜間や救急時の連絡先も聞いておくと、いざという時に慌てずに済みます。
「立てない」「起き上がれない」ワンちゃんにオススメの商品
ほど良い反発感としなやかなストレッチのある撥水性のマット。
温泉鉱石とオーガニック炭を配合した高機能素材"スパオール"を使用。
シニア期のワンちゃんの歩行や動作をサポート。
ワンちゃんの健康寿命をのばすために開発した犬用ラグマット。
お散歩を楽に、寝る時の体への負担軽減に、つらい床ずれや寝たきりを予防。
血流促進とリラクゼーション効果による睡眠の質向上も。
まとめ
以上の通り、老犬が急に立てなくなる原因には、加齢による筋力低下や関節疾患、そして様々な病気が考えられます。
これらの症状は、
「ふらつく」「つまずく」「散歩を嫌がる」「トイレを失敗する」
というような、何かしらのサインが現れます。
飼い主さんは愛犬の変化に気づいたら、無理をさせず、早めに獣医師に診てもらってください。
適切な対応をすることで、愛犬の健康寿命を延ばすことに繋がりますから。