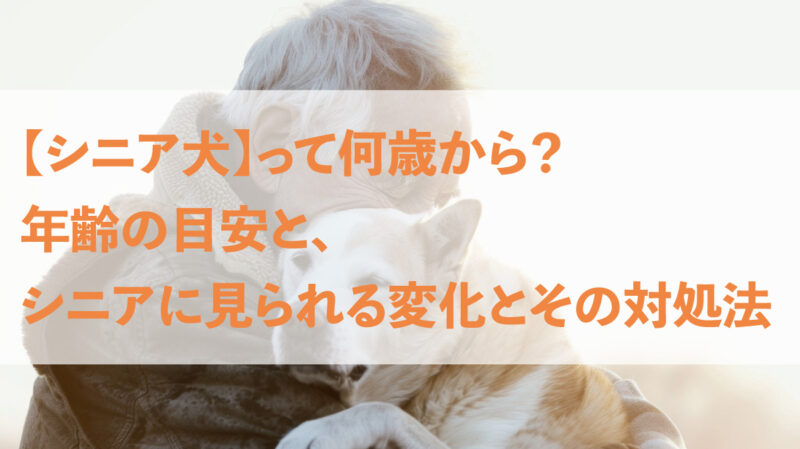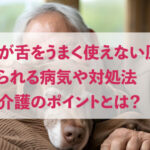愛犬も年を重ねれば、いずれ「シニア犬(高齢犬)」と呼ばれる時期がやってきます。
人間よりも早いスピードで歳を取る犬が、
「何歳からシニア期に入るのか?」
「シニア期にはどのようなケアが必要なのか?」
これらを知っておくことはとても大切なことです。
本記事では、犬の年齢からみるシニア期と、シニア犬に見られる変化とその対処法を解説します。
犬の食事や生活のヒントまで、飼い主が押さえておきたい情報をまとめています。
参考文献・情報源
本記事では、環境省のガイドラインや調査資料、最新の研究知見、獣医師監修の専門サイトなどを参照し、記事の内容をまとめています。
・環境省:「捨てず増やさず飼うなら一生」
・J-Stage:「高齢犬の行動の変化に対するアンケート調査」
・一般社団法人ペットフード協会:「全国犬猫飼育実態調査」
・THE UNIVERSITY OF CHICAGO:「What dogs are teaching us about aging, with Daniel Promislow」

2016年、日本大学生物資源科学部獣医学科卒。同年4月から、東京都内のペットショップ併設の動物病院に勤務。犬・猫・ウサギ・ハムスターの診療業務を行う傍ら、ペットショップの生体管理や、動物病院の求人管理や、自社製の犬猫用おやつやフードの開発に携わる。
2023年より1年間、分院長を経験し、2024年にフリーランス獣医師として独立。現在は診療業務の他、電話での獣医療相談や、ペット用品の商品監修、記事作成など幅広い業務を行っている。
シニア犬って何歳から?シニア期のはじまり
一般的に、犬は7歳前後からシニア期(高齢期)に入ると言われています。
しかし実際には、同じ「犬」でも犬種のサイズ(体重や体格)によって寿命や老化のスピードが異なるため、この年齢は確実とは言えません。
例えば小型犬は寿命が長く、ゆっくり歳を取る傾向がある一方、大型犬は小型犬よりも早くシニア期に差しかかります。
では以下で目安として、何歳頃からシニア期が始まるのかをサイズ別で解説します。
「小型犬」のシニア期
小型犬とは、成犬時の体重が約10kg未満の犬種を指し、チワワやトイ・プードル、ミニチュア・ダックスフンドなどが該当します。
そして小型犬は比較的寿命が長く、シニア期に入るのは「10歳頃」とされています。
実際にシニア期を迎えても元気な子が多く、10歳、12歳を過ぎた犬が活発に動き回ることも珍しくありません。
しかし「まだ若い」と思っているうちに、徐々に老化は進行しますので、10歳を待たずに日頃の健康管理に気を配り始めるといいでしょう。
「中型犬」のシニア期
中型犬は、成犬時体重がおおよそ10〜25kg程度の犬種で、柴犬、コーギー、ビーグル、ボーダーコリーなどが含まれます。
そして中型犬は小型犬よりやや寿命が短めです。
中型犬に該当する犬種は多いため、シニア期の目安は「7〜9歳頃」。
柴犬であれば8歳あたりから白い毛(白髪)が増えたり、寝ている時間が長くなるなど、少しずつ年齢を感じさせる変化が現れることがあります。
中型犬の場合、10歳を迎える頃には人間でいう60代前後と、かなり高齢の域になります。
8歳を過ぎたらプレシニア(シニア手前)期と位置づけ、食事内容や運動量の見直しなどを始めるのがおすすめです。
「大型犬」のシニア期
大型犬は、成犬の体重が25kg以上の犬種を指し、ゴールデン・レトリバー、ラブラドール・レトリバー、秋田犬、グレート・デーンなどが代表的です。
大型犬は小型犬よりも早く老化が訪れる傾向があり、5〜6歳でもうシニアに入るとされています。
例えばグレート・デーンの平均寿命は8歳〜10歳と短く、6歳で人間の約60歳に値し、動きやしぐさに変化が出てきます。
環境省の資料からも、大型犬は7歳頃が高齢期に入る目安とされているため、大型犬の飼い主は5歳を過ぎたらシニアを意識すると良いでしょう。
また、小型犬に比べて発症しやすい疾患(関節疾患や心臓病など)もありますので、早めの健康管理と予防措置を講じてあげてください。
犬のライフステージ
以上のように、犬のサイズ、犬種など個体差によってシニア期は大きく異なります。
犬は人よりも速いペースで成長し、
「子犬」→「成犬」→「シニア犬」
と、年齢とともにステージが移り変わるのです。
以下は、犬のライフステージの目安です。
| 時期 | 特徴 |
| 子犬期(パピー期) | ・成長が著しい幼少期 ・人間で幼児から小学生くらい ・生後半年ほどで急激に成長 ・1年ほどで成犬の大きさに近づく ・「社会化」や「しつけ」を学ぶ大切な時期 |
| 成犬期(アダルト期) | ・心身ともに成熟した大人の犬の時期 ・人間で20代〜40代に相当 ・もっとも活動的で安定した時期 ・健康に気をつける必要あり ・適度な運動とバランスの良い食事が必要 |
| 高齢期(シニア期) | ・人間の中高年から高齢者にあたる ・徐々に老化の兆候が現れる ・過度な運動や遊びはしない ・高齢が進むと介護が必要になる場合あり ・若い頃とは違ったケアや配慮が必要 |
犬も高齢になると思うように体が動かなくなりますので、それぞれのステージに見合った散歩や遊びを心がけましょう。
では続いては、犬を飼っている人とシニア犬の割合について解説します。
日本における犬の飼育頭数とシニア犬の割合
まずはじめに、日本において犬はどのぐらい飼育されているのでしょうか。
日本では、約679.6万頭の犬が飼育されており、年々世帯飼育率は下がっているものの、飼育頭数の下げ幅は縮小しています。(2024年時点)
」.png)
またこの調査データの通り、そのうち7歳以上のシニア犬は全体の約54.9%、およそ373.1万頭を占めています。
これは飼育されている犬の半数以上が「シニア期」に入っている、愛犬の「高齢化」に直面する飼い主も年々増えていることを示しています。
そして、犬の健康管理や生活を維持するためには、日頃から様々なケアが必要です。
しかしながら人間の高齢化も進んでいることから、犬の行動や生活面での変化に気づかず、体調を崩すケースも増えています。
とはいえ、犬を飼いたいと思う人の多くは、
「日頃の生活に癒しや安らぎが欲しい」 「生活を充実させたい」
と、犬と生活することを強く望んでいるようです。
(全国犬猫飼育実態調査「ペット飼育意向のきっかけ」より)
犬の年齢と人間換算年齢の例
犬の年齢を人間に例えると何歳くらいになのか、気になりますよね。
既に述べた通り、犬の場合、犬種や体の大小によって老化のスピードが異なるため、一概に「〇〇歳」とは言えません。
ですが、以下のような年齢の目安はあります。
| 犬の年齢 | 大型犬(人の年齢) | 小・中型犬(人の年齢) |
| 1歳 | 12歳 | 15歳 |
| 2歳 | 19歳 | 24歳 |
| 3歳 | 26歳 | 28歳 |
| 4歳 | 33歳 | 32歳 |
| 5歳 | 40歳 | 36歳 |
| 6歳 | 47歳 | 40歳 |
| 7歳 | 54歳 | 44歳 |
| 8歳 | 61歳 | 48歳 |
| 9歳 | 68歳 | 52歳 |
| 10歳 | 75歳 | 56歳 |
| 11歳 | 82歳 | 60歳 |
| 12歳 | 89歳 | 64歳 |
| 13歳 | 96歳 | 68歳 |
| 14歳 | 103歳 | 72歳 |
| 15歳 | 110歳 | 76歳 |
| 16歳 | 117歳 | 80歳 |
| 17歳 | 124歳 | 84歳 |
環境省:「捨てず増やさず飼うなら一生」より抜粋
この一覧から、人が1歳の時点で犬は中学生ぐらいに、7歳を迎える頃には中年〜高齢にあたることがわかります。
そして大型犬は1年で7歳、小型・中型犬は4歳と、犬によって1年の長さは大きく異なります。
それぞれのシニア期の始まりとは
同じ「犬」でも、犬種のサイズ(体重や体格)によって寿命や老化のスピードが異なります。
小型犬は寿命が長く、ゆっくり歳を取る傾向がある一方、大型犬は早くシニアに差しかかります。
ただし、犬のサイズを分類する際に明確な基準はありません。
そのため、あくまでも一般的な目安として、それぞれ何歳頃からシニア期が始まるのかを解説します。
「小型犬」のシニア期
小型犬とは、成犬時の体重が約10kg未満の犬種を指し、チワワやトイ・プードル、ミニチュア・ダックスフンドなどが該当します。
そして小型犬は比較的寿命が長く、シニア期に入るのは10歳前後とされています。
実際にシニア期を迎えても元気な子が多く、10歳、12歳を過ぎた犬が活発に動き回ることも珍しくありません。
しかし「まだ若い」と思っているうちに、徐々に老化は進行しますので、10歳を待たずに日頃の健康管理に気を配り始めるといいでしょう。
「中型犬」のシニア期
中型犬は、成犬時体重がおおよそ10〜25kg程度の犬種で、柴犬、コーギー、ビーグル、ボーダーコリーなどが含まれます。
中型犬は小型犬よりやや寿命が短めです。
シニア期の目安は7〜9歳頃で、柴犬であれば8歳あたりから白い毛(白髪)が増えたり、寝ている時間が長くなるなど、少しずつ年齢を感じさせる変化が現れることがあります。
中型犬の場合、10歳を迎える頃には人間でいう60代前後、かなり高齢の域になります。
8歳を過ぎたらプレシニア(シニア手前)期と位置づけ、食事内容や運動量の見直しなどを始めるのがおすすめです。
「大型犬」のシニア期
大型犬は、成犬の体重が25kg以上の犬種を指し、ゴールデン・レトリバー、ラブラドール・レトリバー、秋田犬、グレート・デーンなどが代表的です。
大型犬は小型犬よりも早く老化が訪れる傾向があり、5〜6歳でもうシニアの入り口に立つとされています。
例えばグレート・デーンの平均寿命は8歳〜10歳と短く、6歳で人間の約60歳に値し、動きやしぐさに変化が出てきます。
環境省の資料からも、大型犬は7歳頃が高齢期に入る目安とされているため、大型犬の飼い主は5歳を過ぎたらシニアを意識すると良いでしょう。
また、小型犬に比べて発症しやすい疾患(関節疾患や心臓病など)もありますので、早めの健康管理と予防措置を講じてあげてください。
シニア期に入った犬にしてあげて欲しいこと
愛犬がシニア期に差しかかったら、心がけて欲しいポイントがあります。
大切なのは、若い頃と同じように接するのではなく、年齢に合わせたケアをしてあげることです。
以下でそれぞれご紹介します。
定期的な健康診断と日々の健康チェック
シニア期に入ったら、若い頃以上にこまめな健康チェックが欠かせません。
動物病院での定期健診は最低でも年に1回、可能なら年2回程度受けるのがおすすめです。
シニア期を迎えたあたりからは、血液検査やレントゲンなどを含むシニア向けの健康診断を利用し、潜在的な病気の早期発見に努めましょう。
普段から以下の点を観察してみてください。
・食欲や水を飲む量
・排せつ
・歩き方
・呼吸の様子
・目の動き
少しでも「おかしいな」という変化に気付いたら、早めに獣医師に相談してください。
食事内容を見直し、適正体重を維持する
人と同じく、犬も高齢になると代謝が落ち、太りやすくも痩せにくくもなります 。
そのため、カロリー控えめ・栄養バランスの取れたフードに切り替え、適正な体重をキープしてあげましょう。
肥満は関節炎や心臓病、糖尿病など、様々な病気の要因となるため注意が必要です。
ある研究によると、生涯を通じて痩せた状態を維持した犬は、太った犬よりも平均寿命が約2年長かったそうです。
シニア向けに推奨されている「高タンパク・低カロリー」のもので、愛犬の健康状態に合わせて適切なフードを選びましょう。
もしも、「犬がうまくご飯を食べれない」「口からボロボロこぼす」という時は、体に何か問題があるかもしれません。
詳しくは以下の記事で解説しています。
-

-
老犬が舌をうまく使えない原因。考えられる病気や対処法:食事介護のポイント
老犬がうまくご飯を食べられません。 何か良い方法はありますか? 老犬が食事を残したり、舌をうまく使えなくなっていませんか? 実はこれ、加齢や体調の変化が関係している可能性があります。 シニア期に入った ...
続きを見る
無理のない適度な運動
運動不足は肥満や筋力の低下、認知機能にも影響します。
そのためシニア犬でも適度な運動を、無理のない範囲で行いましょう。
散歩の距離を短くしたり回数を分けるなど、犬の体調や足腰などの様子を見ながらほど良い運動をします。
夏場は熱中症や熱射病など特に注意が必要です。早朝など地面が暑くない時間帯に連れていきましょう。
高齢になると認知症も懸念されるので、室内遊びは知育玩具を使って認知予防をするのもおすすめです。
快適に過ごせる生活環境を整える
シニア犬には安全で快適なお家が必要です。
高齢になると体温が調節しにくくなるので、室温管理に気を配り、冬場は寒さ対策、夏場は暑さ対策を徹底します。
それに外飼いの場合は、外で過ごすことが辛くなってきますので、少しずつ家の中で過ごす機会を増やしていきましょう。
また、お家の中で転んだりしないように、滑り止めマットやステップ(階段)などの設置も必要です。
高齢になると視力や聴力も低下するので、家具の配置を変えるとぶつかったり怪我をする恐れがあります。
シニア期に入る前に、なるべく早い段階で環境を整えてあげましょう。
スキンシップを大切にする
シニア犬になると、あまり動かなくなったり眠っている時間が増えます。
すると飼い主と接する機会が少なくなり、その分スキンシップの時間も減ります。
犬はひとりでいることが多くなると、寂しさから元気もなくなってしまいますので、以前よりも気を配ってあげることです。
「声をかける」「体を撫でる」「目を見てにっこり微笑む」
このどれもが犬に安心感を与えます。
昼寝している犬の近くで静かに本を読んだり、家事をしながら声をかけたりするのも、立派なスキンシップのひとつです。
意図的に一緒に過ごす時間を心がけましょう。
老化は突然やってくる?シニア犬に見られる変化と対処法
「ついこの前まで元気だったのに、急に老け込んだように見える…」
このように感じる飼い主さんも少なくないはず。
犬の老化現象は「ある日突然訪れる」のではなく、人よりも歳を取る速度が早いことから「日々進行している」のです。
ただ、ゆっくりとした変化なために気付かず、突如老けたように感じてしまうのです。
そこでここでは、シニア犬に見られやすい体や行動の変化の例と、それぞれの対処法について解説します。
※以下は獣医師の知見と、J-Stage「高齢犬の行動の変化に対するアンケート調査」を元にまとめています。
毛や見た目の変化
【主な症状】
- 口元や眉のあたりに白い毛(白髪)が増える
- 毛艶が衰える
- 皮膚のハリがなくなる
対処法
ブラッシングや保湿ケアを行い、皮膚や毛の健康を保つようにします。
白髪自体は自然な老化現象なので心配いりませんが、美容面ではシニア用の低刺激シャンプーを使いましょう。
視力・聴力の低下
【主な症状】
- 目が白く濁って見える(白内障の疑い)
- 呼んでも反応が鈍い、気づかない(難聴の兆候)
対処法
視覚や聴覚が衰えると、犬は不安を感じたり驚きやすくなることがあります。
「家具の配置を変えない」「ゆっくり近づいて気配を伝える」「身ぶり手ぶりで合図を送る」
など、犬が安心できる働きかけをしましょう。
視力が落ちても嗅覚は最後まで残ることが多いので、匂い付きのおもちゃを使った遊びもおすすめです。
動きや体力の変化
【主な症状】
- 寝ている時間が増える
- 動きがゆっくりになる
- 散歩で長い距離を歩けなくなる
- 段差を嫌がる
- 動きたがらない
※これらの原因には、筋力の低下や関節の痛み、心肺機能の衰えなどがあります。特に関節の変形(関節炎・変形性関節症)はシニア犬に多いです。
対処法
無理な運動を避けて、筋力を維持するための適度な運動、滑り止めマット、段差にスロープの設置、必要に応じて関節用のサプリメントや治療が考えられます。
散歩は愛犬のペースに合わせて、途中で休憩を入れるようにしましょう。
排泄の変化
【主な症状】
- トイレの失敗が増える
- 尿の回数が増える
- 我慢できず漏らしてしまう
- 水を大量に飲むようになる
※排泄パターンの変化も高齢犬によく見られます。腎臓機能の低下やホルモン変化、認知機能の低下など様々な原因が考えられます。
対処法
頻繁にトイレに連れて行く習慣をつけ、室内にトイレシーツを置いたり、おむつやマナーウェアをつけます。
急な排泄変化は病気のサインの場合もあるので、場合によっては獣医師に相談し、尿検査や血液検査で原因を調べてもらいましょう。
また、室内で粗相してしまっても決して叱らずに。
吠え方や犬自身の反応
【主な症状】
- 情緒不安定になりやすい(夜泣きする、クーンとなく、攻撃的になる)
- 自分がどこにいるかわからない様子(ぐるぐると同じところを回る、ドアを間違えたりする)
- 呼んでもボーっとして反応が遅い
- 今まで平気だった刺激に驚きやすくなる
- おすわりやトイレを忘れる
対処法
まずは生活環境と生活リズムを安定させ、極端な環境の変化を避けます。
「朝、日光を浴びさせる」「適度に体と頭を使わせる」といった工夫をして、夜しっかり眠れるようにします。
症状が重い場合は、獣医師に相談して適切な処置を受けましょう。
大事なのは、家族で介護負担を分散し、飼い主さん自身も無理をしすぎないように気を付けることです。
こうした変化は、犬によって現れる程度や時期が異なります。
「老化かな?」と思うサインを早めに察知し、小さな変化にも寄り添ってあげましょう。
いつからフードを変えるべき?シニア犬の食事
最後に、シニア犬の食事について。
「いつ頃からフードをシニア用に変えたらいいの?」という疑問は、多くの飼い主さんが抱える問題ですよね。
市販のドッグフードには、「高齢犬用(シニア用)」と記載されており、7歳以降とされていることが多いです。
これは平均的な目安であり、必ずしも7歳の誕生日を迎えたらフードを変えなければいけない、ということではありません。
小型・中型犬は7歳を目安とし、大型犬は5歳頃からシニア用のフードに切り替えますが、犬の体調や体重の変化、獣医師からの指摘を踏まえた上で決めるのをおすすめします。
ただ、フードを変えたことにより、味や匂いを嫌ったり、歯や顎に問題があり食べてくれない場合があります。
そのような時は、フードを温めたり、ふやかして柔らかくしたり、どうしても口に合わない場合は作ってあげましょう。
食欲がなければ病気の可能性もあるので、その際は病院へ行って診てもらいましょう。
まとめ
以上、犬の年齢からみるシニア期と、シニア犬に見られる変化と対処法をお伝えしました。
人と同じく、犬も老化は避けられないものです。
しかし、老いを受け入れ、上手に付き合うことで、愛犬との生活は豊かになります。
シニア期に入った愛犬には、これまで以上の愛情と気遣いをもって接し、一日一日を大切に過ごしてください。
年をとっても愛犬はかけがえのない家族ですので、「いつまでも元気でいてね」という気持ちを込めて、今日からできることを始めましょう。