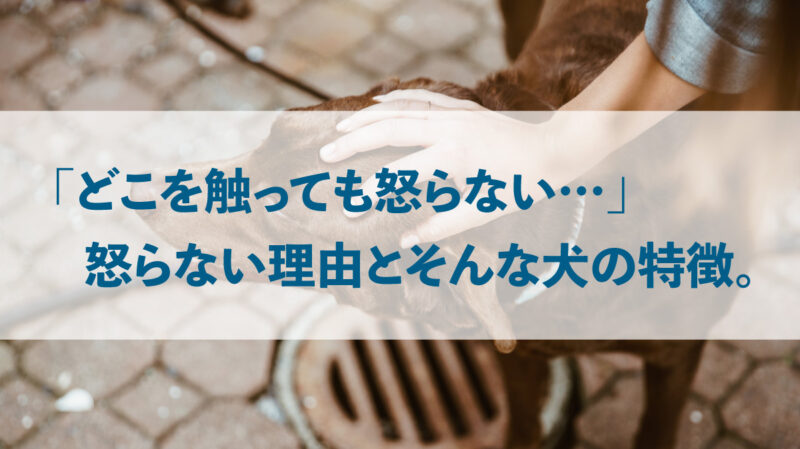お腹、耳、尻尾など、どこを触っても怒らない犬は許してくれている証拠でしょうか?
犬がどこを触っても怒らないのは、単なる「我慢」ではなく『信頼』の証かもしれません。
特に耳やしっぽなど、犬にとってデリケートな部分に触れても嫌がらないなら、それは飼い主への安心感を示している可能性があります。
とは言え、実際のところ本当にそう言い切れるのでしょうか?
本記事では、犬がどこを触っても怒らない理由と、そんなワンちゃんに見受けられる特徴を解説します。

2016年、日本大学生物資源科学部獣医学科卒。同年4月から、東京都内のペットショップ併設の動物病院に勤務。犬・猫・ウサギ・ハムスターの診療業務を行う傍ら、ペットショップの生体管理や、動物病院の求人管理や、自社製の犬猫用おやつやフードの開発に携わる。
2023年より1年間、分院長を経験し、2024年にフリーランス獣医師として独立。現在は診療業務の他、電話での獣医療相談や、ペット用品の商品監修、記事作成など幅広い業務を行っている。
犬がどこを触っても怒らないのは「信頼している」から
犬がどこを触っても怒らないと言われてる理由を詳しく調査しました。
すると「怒らない」と述べる大多数の人は、犬からとても信頼されていることが分かりました。
そもそも、
「なぜうちの犬はどこを触っても怒らないの?」
と疑問に思う飼い主は、周囲やネットの情報から「犬は体に触れると怒るもの」と誤った認識をしています。
それなのに、
「うちの犬は鼻を撫でても耳を触っても怒らないし、反対にじっとしてるしヘソ天して喜んでいる」
と、聞いた話と真逆の行動をとっていることに、不思議に思っています。
こうした情報が一致しないことから、
「うちの犬は変なの?」 「珍しいタイプ?」 「ただのおバカちゃん?」
と少し不安に思い意見を求めている様子が伺えます。
しかしながら、『犬を飼っている』または『犬のことをよく知る人』からすれば、これはとても微笑ましいことで、飼い主と犬の関係が築けている証であって、反対に犬から信頼されていて羨ましいことなのです。
「触る」「撫でる」は犬との絆が深まる?
飼っているワンちゃんの体を触ったり撫でる行為は、犬との関係性に大きく影響します。
というのも、犬は撫でられることにより、愛情や安心感が得られて気持ちがリラックスするのです。
またこの調査によると、ペットとの絆を深めるために、「撫でる、触るなどのスキンシップをとる」と答えた人は最も多く、このようなスキンシップを通じて、「ペットとの絆ができている」と感じている人は9割を超えていました。
ただ、犬は話すことができないため、「人が一方的に感じている」ようにも思えます。
ですがこうしたスキンシップを通じて、犬の行動や性格の変化が現れており、そのうち約7割もの人が、
「犬が近くに寄ってくるようになった」
と、実際に絆ができていることを体感しています。
どこを触っても怒らない犬の特徴
どこを触っても怒らないワンちゃんには、何か共通する特徴があるのではないか?と思い、詳しく調べてみました。
するとそこには、共通する特徴があることがわかりました。
以下で、「どこを触っても怒らない犬の特徴」を詳しく解説します。
まだ幼い子犬だから
1つ目は、ワンちゃんが小さな子犬だからです。
人の子も小さい頃は、パパやママと戯れて遊んだりすることが大好きですよね。
ワンちゃんも同じく好奇心旺盛で、人と触れ合うことを楽しみます。
子犬の頃は社会性を学ぶ大切な時期なので、人とのスキンシップが楽しいと感じれば、触られることを嫌がらなくなります。
また、子犬はまだ本能的な警戒心が少なく、攻撃的な態度を取ることがほとんどありません。
成長するにつれて、触られることに慣れていれば、そのまま穏やかな性格の犬になることが多いでしょう。
そのため、小さいうちからたくさん撫でて触れ合い、優しく声をかけながら接することで、どこを触られても怒らない犬に育ちやすくなります。
ただし、子犬のうちは、
・痛みの感覚が鈍い
・嫌なことへの意思表示が少ない
など、まだ「怒る理由を知らない」だけでもあります。
そのため、無理に触るのではなく、優しく触ることを意識すると良いでしょう。
おとなしくて優しい性格だから
2つ目は、その子がおとなしくて優しい性格だからです。
犬の性格にも個性があり、警戒心が強く敏感なタイプの子もいれば、人に撫でられるのが大好きで何をされても平気な子もいます。
もともとおっとりした性格の犬は、人に触れられることに対してあまり抵抗がなく、人とのスキンシップを好む傾向があります。
こうした犬は、飼い主や周囲の人に対して信頼を寄せており、また警戒心が少ないところがあります。
特に、幼い頃からたくさんの人に触れられて育った犬や、しっかり社会化ができている犬は、触られることを心地よく感じることが多いです。
もちろん、どんなに性格が優しくても、嫌なことを繰り返されると警戒するようになります。
ストレスが溜まっていたり、体調が悪いときもあるので、普段から犬の様子をよく観察しましょう。
実際に、「犬が触っても怒らない」ことを動物病院に問い合わせたところ、家族が犬の変化に気付きやすくなり、診察もスムーズになるそうです。
体のどこを触っても怒らないのは性格的なことだとは思いますがとても良い事ですね!
若い頃から全身触られることに慣れておくとご家族様が変化により早く気付くことができたり、
ご診察が必要な際も検査や処置がスムーズに行うことにもつながります。
引き続きわんちゃんとのコミュニケーションを大切にたくさん撫でてあげてくださいね。
原宿犬猫クリニックからの返信より
原宿犬猫クリニック様、丁寧なご回答ありがとうございました。
飼い主をよく理解している
3つ目は、飼い主をよく理解しているからです。
そもそも、飼っている犬のどこを触っても怒らないのには、飼い主がその犬の気持ちや、好き嫌いをしっかり理解しているからです。
犬によっては、「撫でられて気持ちいいところ」と「触られるのが苦手なところ」があります。
例えば、頭や背中を撫でられるのを好む犬もいれば、お腹を出して撫でられるのが好きな犬もいます。
一方で、足先や尻尾、耳の内側など、敏感な部分を無理に触られるのを嫌がる犬も少なくありません。
また、ちゃんとしつけができていると、犬もむやみに吠えたり唸ったりしなくなります。
基本的なしつけ方は、良いことをしたらいっぱい褒めて、悪いことをしたら反応しないことです。
例えば、犬が吠えたり噛んだりした時に、手を振ったり「やめて」と嫌がるのは、実は逆効果。
犬は勘違いして喜んでしまいます。
かといって怒るのも同じで、このような場合は、反応せずにその場を離れるのが正解です。
そして犬と散歩をする時は、前を歩かせるのではなく並走するのが、正しい犬のしつけ方です。
⚫︎飼い主が立ち止まった時、犬も同じく止まったらおやつをあげる。
⚫︎進行方向とは違う方へ歩き出したらリードを引っ張る。
このようにして、「今の行動は良いことだ!」「これはやってはいけないことなんだ…」を認識させます。
行動と反応をセットにすることで、うまくしつけられるようになり、犬は飼い主のことをちゃんと理解できるようになるのです。
そして飼い主自身も、犬が何を求めているか分かるようになっていきます。
犬が怒る時の仕草
反対に犬が怒っている時は、相手を威嚇したり攻撃しようと構えます。
それは主に、散歩中に通りすがる人や犬など「動くモノ」に対して行います。
もし、体を触る際や、通行人や犬などに以下のようなサインを見せたら、一度体を触ることを中止したり、その場から離れるといった対処をしましょう。
犬が怒ったり警戒する時の仕草
- 唸り声をあげる
- 牙をむき出す
- 耳が前を向く
- 毛を逆立てる
- 鼻にシワを寄せる
- しっぽをピンと立てる
こうした行為をする時が、その対象に向けた怒りや警戒のサインを示しているのです。
ただし、威嚇行動をするのは飼い主をはじめとする、自己の群れを守ろうとする防衛本能です。
「なんか犬が怒ってる…」
と感じた時は、その場から離れて犬を落ち着かせましょう。
こうした行動においても、犬との信頼関係を築くことにつながります。
またほかにも、体を触って怒る場合は、何か病気で痛みを抱えているケースもあるので、病院に症状を伝えて相談してみてください。
犬が触られるのを嫌がる部位とその理由
犬は全身を触られても平気なように見えて、実は「ここはちょっと苦手…」と感じている部位もあります。
たとえば、しっぽやマズル(鼻先から口にかける部位)は多くの犬が敏感に反応するところで、これらには神経が集中しているために触ると嫌がるのです。
また、過去に嫌な経験をした場所を触られると、その記憶から嫌がることもあります。
どこでも触れる犬は、すばらしい信頼関係が築けている証拠です。
ただ、犬には苦手な部分があることを認識しておくと、突如犬が嫌な反応をしたときに対処しやすくなります。
犬が触られることに慣れるためのトレーニング方法
もしも飼っている犬が体を触られることに慣れていない場合は、段階を踏んで少しずつ信頼を深めていきましょう。
以下でそのステップを解説します。
- 静かな場所で始める
- 人の手に慣れさせる
- 触りながらご褒美をあたえる
- 首輪を持ってご褒美をあげる
- 犬の反応をしっかり観察する
静かな場所で始める
飼い主の声や動きに集中できるよう、刺激の少ない静かな場所で始めましょう。
人や物音が少ない場所、寝起きや遊びの後など、犬が落ち着いているタイミングに行います。
触っても嫌がらないのは、飼い主を信頼していることを意味します。
だからまずは、犬と飼い主がマンツーマンになることが大事です。
人の手に慣れさせる
人の手を怖がる犬も少なくありません。
「ハンドシャイ」という言葉があるように、手を伸ばしたり触られることを怖がってしまう症状です。
そのため、人の手は怖くないと覚えさせるために、おやつを手の平に乗せて食べさせてあげます。
手の平に乗せても食べてくれない場合は、床においてみると食べてくれます。
おやつをあげる時は「いい子だね」と声をかけてあげましょう。
触りながらご褒美をあたえる
犬がおやつやご飯に夢中になっている時に、優しくゆっくり触ってみましょう。
触る場所は比較的犬が嫌がらない、
・背中
・頭
・首周り
・肩
この辺りに触れてみて、その子が嫌がらない場所にします。
食べ物はたくさん撫でられるように、ふやかしたフードや舐め続けられるものにします。
もしも途中で嫌がったり怒ったりした時は、一度撫でるのをやめること。
無理に続けると、余計に触られるのを嫌がってしまいます。
触っている時の犬の姿勢は、座っていても伏せていてもどちらでもいいです。
首輪を持ってご褒美をあげる
犬が首輪を掴むのを嫌がるのは、首周りを触られたくないからです。
わしづかみにすると嫌がるので、顔の下から、または横から軽く掴むようにします。
嫌がらなければ、掴む長さを2秒、3秒と伸ばしていき、褒めてからご褒美をあげます。
もしも首輪を掴むのを嫌がるようであれば、前のステップに戻り、体に触れる時間を増やしましょう。
首輪を掴むことができれば、散歩や病院などで犬を落ち着かせることもできます。
犬の反応をしっかり観察する
飼い主が犬に触れたくても、それはあくまでも人の都合です。
犬はひとりで寝たかったり、気分によって触られたくない時もあります。
ただ、先に述べたように、病院など飼い主以外の人が触れる機会があるので、毎日少しずつ、人の都合で決まった時間に行うようにしましょう。
こまめにスキンシップを行い続ければ、犬も触られることに抵抗を感じにくくなります。
飼い主は諦めず、継続することがとても重要です。